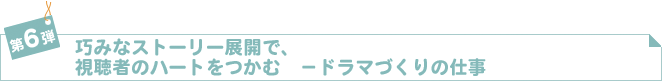HOME > 特集記事 > 中・高校生に送る 業界特集 > 「巧みなストーリー展開で、視聴者のハートをつかむ - ドラマづくりの仕事」
ドラマ「13歳のハローワーク」の制作現場を取材!
1%でも多くの視聴率を獲得するために、実力と人気が伴った、できるだけ注目度の高い俳優を起用し、話題づくりを行うなど、特にテレビ局がしのぎを削っているのが「ドラマ」です。
ここでは、そのドラマづくりの仕事について、ご紹介します。
ドラマをつくるにあたって、どのような職種のスタッフたちが働いているのでしょうか?
ドラマの中では出演者の存在しか分かりませんが、番組の最後に流れるエンディングクレジット(下から上に、あるいは右から左に流れる字幕)を見ると、たくさんの人たちが関わっているということだけは、なんとなく分かりますね。
では、ドラマづくりの陰で、誰がどのような役割を果たしているのでしょうか?具体的に挙げてみましょう。

番組をつくるにあたっての総責任者。企画から脚本家との台本づくり、出演者・スタッフの選定、お金の管理、撮影現場の立会い、編集のチェック、番組の宣伝活動、DVDやグッズのコンテンツ展開まで、全体をマネジメントする。

中川慎子さん

浅井千瑞さん
 アシスタントプロデューサー(AP)
アシスタントプロデューサー(AP)
プロデューサーの補佐役。現場での役者ケアや編集スケジュールの管理、脇役などのキャスティング、そして番宣活動の仕込みなど、その業務は現場に留まらず、ドラマにおける最も忙しいポジションのひとつである。
番組制作現場の総指揮者。企画や脚本に沿って番組ができるよう、現場を牽引する。
出演者の演技指導から、技術、美術、編集、MA作業に至るまで、ドラマの内容が視聴者に効果的に伝わるよう作品全体を総合的に演出していく。

高橋伸之さん

塚本連平さん
ディレクターの補佐役。演出面における監督の意向を汲んで、そのために必要なありとあらゆる業務を担う。
技術、美術、制作部などとの内部交渉はもちろん、外部との渉外、現場でのスケジュール調整、など撮影現場で起こる全ての雑事が仕事といっても過言ではない。そのハードな修行期間を経て、晴れてディレクターと昇格していく。

吉原通克さん
ドラマの核となる脚本(台詞と描写説明)を書く人。シナリオライターともいう。
プロデューサーやディレクターと打ち合わせを重ね、推敲し、物語を構築していく。

脚本家
大石哲也さん
役を演じる人。主演、助演は、実力と知名度の高い俳優やタレントが務め、ドラマをけん引していく。
撮影期間中は朝から晩までタイトなスケジュールで撮影をこなす一方で、それ以外にも番組PRのために取材などやバラエティ番組への出演を行うなど、かなりの多忙を極める。
 制作部
制作部
監督のイメージをもとにロケ場所を選定。それに伴いロケ使用時に必要な許可取りを行い、撮影がスムーズにおこなえるように環境を整える。
また撮影時のキャスト・スタッフ食事の用意、撮影場所での人員整理、ロケ場所の地図作成などその業務は多岐に渡り、「現場の母」といわれることも。
 スケジューラー
スケジューラー
脚本を読んで撮影に必要な時間を割り出し、そこに役者のスケジュール、ロケ場所のスケジュール、編集スケジュール等をかけあわせて、撮影スケジュールを組み立てる専門職。

村田淳志さん
ドラマを撮影するカメラマン。監督と相談しながら、効果的なカメラワークを考える。
ドラマのシーンに応じて、心理描写や時間の流れなどを光で表現する。
出演者の台詞や周囲の音などを録音し、音の素材を集める。
 ビデオエンジニア
ビデオエンジニア
映像機器に精通し、明るさの調整や不具合の対応などの管理を行う。
撮影した映像素材をストーリーにしたがってつなげたり、さらに加工して作品としての完成度を高める。
監督の要望を汲みながらスタジオセットやロケセットをデザインし、ビジュアルの世界観を作り上げていく。

村竹良二さん

森永牧子さん
 美術/大道具、小道具担当
美術/大道具、小道具担当
出演者の役柄に応じて、ヘアスタイルを整え、メイクをする。
ヘア&メイク同様、出演者の役柄に合った衣装や小物を準備する。
 マスター
マスター
オンエア前に、内容に不備がないか最終チェックを行う。
 広報(番組宣伝)担当
広報(番組宣伝)担当
より多くの人に視聴してもらうために、さまざまなメディアを活用してドラマの認知度を高める。
⇒ 参考:映画宣伝
 コンテンツ担当
コンテンツ担当
作品のHP制作や作品から派生したグッズを制作し販売する。
このように、ドラマづくりには、びっくりするほど多くの職種とスタッフが関わっているのです。他にも、CG制作者や選曲効果などさまざまなスタッフがいます。これらのスタッフは、ドラマの内容等によって構成が変わります。
もし、文化祭で演劇を行うことになったら、“晴れの舞台”までに、何をどのような順番で行いますか?
まずは、題材。そう、企画ですね。みんなで考えて会議を行い、どの題材を扱うか決まったら、台本をつくります。そして、役割を決めて、衣装や舞台に必要な材料をそろえて、何度も練習を重ねて本番に挑む。というように、何となくイメージできますね。文化祭では、これらのことを全部自分たちでこなしますが、ドラマは比べものにならないくらい大掛かりなので、仕事が細分化されているのです。
では、ドラマづくりの流れを見ていきましょう。
その前に、テレビ番組がどのようにして成り立っているのか、知っていますか?
テレビ局は、たとえば「金曜日の21時~22時の時間枠」という商品を売ることで、機材やスタッフの人件費など制作にかかる経費はもちろん、会社を維持するための費用をまかなっています。
この「時間枠」は、主に広告代理店が購入し、それを企業に売ります。「時間枠」を購入した企業はスポンサーとして、テレビ局に高い視聴率が期待できそうな番組をつくってもらいます。同時に、番組の合間にCMを流すことで自社商品を多くの人に知ってもらい、売上につなげるという仕組みになっています。
プロデューサーが中心となり、時にはテレビ局の編成部、または脚本家などと時勢や想定する視聴者の好み、スポンサーや起用を考えているタレントのイメージなど、あらゆる角度からアイデアを練ります。
↓
方向性が決まったら、脚本家と打ち合わせを重ね、設定を決めこみ、脚本におこしていきます。
↓
物語の骨子が決まったら、役にあった俳優・女優をキャスティングする作業を行います。また同様にその企画にあったスタッフたちを集める作業をします。
↓
ドラマの内容が具体的になってきたら、スタジオのセット(美術)をつくり始めます。屋外での撮影を伴う場合は、ロケハン(ロケーション・ハンティング)を行い、撮影場所を選定します。また、アパレル会社に、出演者が着る衣装の協力依頼を行うなど、必要なものをそろえていきます。
↓
ドラマづくりに関わるスタッフが、一堂に会します。企画内容などを説明してスタッフ全員の意思疎通を図ります。各ポジションのスタッフの自己紹介も行い、各人、ドラマ撮影チームの一員として、気持ちが一気に高まります。
↓
リハーサル室にて、台本の読み合わせを行います。このときは、出演者は椅子に座ったまま台詞を読みあげ、それに対して演出家が声の強弱や感情表現について指示します。
↓
本番前に完成した美術セットを使って、リハーサルを行います。最初は撮影は行わず、出演者の動きとカット割りを確認します。同時に、各スタッフもここで配置や手順を細かく打ち合わせします。
このような段階を経て、本番同様にスタッフを配置し、カメラを用いてリハーサルを行います。監督、出演者はカット割りと動きを、技術スタッフは照明やマイクなど機材の動作を最終チェックします。
↓
出演者の立ち位置、動きが決まったら、企画意図に合わせて撮影のアングルやフレーミング、照明の位置などを決めていきます。
↓
準備が整ったら、いよいよ本番です。撮影した映像はその場でチェックし、セリフの長さや演技の完成度、さらに不必要なものが写り込んでいないかなどを確認します。もしNGがあれば、撮影し直します。
↓
スタジオやロケで撮影した映像素材から必要なシーンを切り出してつなげ、さらに効果音やBGMを加えて、ドラマを完成させます。
↓
オンエア前に、マスター(送出業務)スタッフが最終的なチェックを行います。問題がなければ、ドラマを放映する地方各局にビデオテープを送ります。
普段、何気なく見ているドラマは、このような流れでつくられています。ドラマにもよりますが、1クール(3か月)放映するドラマで、企画の段階から含めると半年から1年かけてつくられ、お茶の間に届けられるのです。
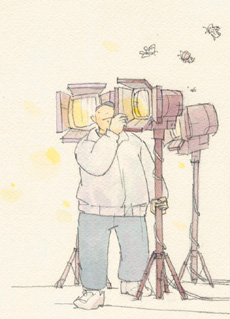
ドラマ制作の仕事に就くために就職先としてまず考えられるのが、テレビ局です。将来、プロデューサーやディレクターとして、全体をまとめる仕事がしたい人にはピッタリです。テレビ局への就職は、入社試験の受験資格として、ほとんどの場合、大学以上の学歴が要求されます。また、特別なスキルや資格は必要としないので、高校から大学へ進学する際、学部・学科は自分の好きな分野を自由に選択できます。
撮影や音声、照明など、技術スタッフとして一線で活躍したい人には、テレビ局の他、番組制作会社への道があります。自分の進路が明確であれば、映像制作系の専門学校でスキルを身に付けて就職する方が、夢実現への近道といえます。
あるいは、番組制作会社でアルバイトからスタートして、そのまま就職するという方法もあります。いわゆる“たたき上げ”で、お金をもらいながら学べるという意味では、最も効率的かもしれません。
この他、ヘア&メイクやデザイナーなどは、ドラマ制作スタッフとは別の専門的な知識とスキルが要求されるので、大学や専門学校で学び、必要な素養を身に付けた上で、ドラマの仕事を請け負っている会社への就職を目指します。
- 《主な就職先》
- テレビ局
- 番組制作会社
- 美術会社
- 撮影技術会社
- ポストプロダクション
- 音楽制作会社
- 音響効果会社
- モデル事務所
- 脚本家事務所 など
制作協力:テレビ朝日
中・高校生に送る「業界特集」
-
地域のくらしをバックアップする
司法書士の仕事 -
生活空間と街をつくる
総合建設業の仕事 -
巧みなストーリー展開で、視聴者のハートをつかむ
ドラマづくりの仕事 -
大海原が人生のステージ
海運の仕事 -
“キレイ”をつくるプロフェッショナル
美容業界での働き方 -
おいしい仕事、教えます
料理業界での働き方 -
“音楽”を仕事にしたい人に
音楽業界での働き方 -
観光・ホテル産業に関わる仕事