HOME > 特集記事 > P.S.明日のための予習 13歳が20歳になるころには? > いろいろな働き方の選択
[INDEX]
- 1. 雇用の形の多様化と「就職」について
- 2. 起業のすすめ
-
3. NPOという選択肢
- 3-1 大相撲協会や骨髄バンクもNPO
- 3-2 日本のNPOの現状
- 3-3 官から民という大きな流れ
- 3-4 これから予想されるNPOの仕事
- 3-5 営利企業のNPO化も
- 3-6 NPOの課題
- 3-7 【結論】:NPOという選択肢
- 4. 「資格」をどう考えるか
- 5. 「つなぎのバイト」をどう考えるか
- 6. 趣味の弊害について
3. NPOという選択肢
NGOは「非政府組織(Nongovernment organization)」、NPOは「非営利組織(Nonprofit organization)」の頭文字をとった略称だ。 ただし両者はほとんど同じもので、非営利というニュアンスが強い場合にNPOと呼ばれ、国際的な活動で非政府組織というニュアンスが強い場合にNGOと呼ばれる。 ここでは統一して「NPO」という呼び方を使うことにする。 NPOは、政府・自治体の組織でもなく、企業でもない新しい組織として注目されているが、おもにマスメディアなどによって、阪神大震災などで活躍した草の根的な小さなボランティア組織、というイメージが先行してしまった。
しかし、非営利組織は、公益法人や宗教法人、医療法人、教育法人など、すでにたくさん存在してきた。 たとえば多くの私立学校、医療法人、それに大相撲協会や骨髄バンクもNPOである。 また、NPOはボランティア団体ではない。 もちろんボランティア活動を行うこともあるが、ほとんどのNPOは収入を得ている。 非営利という意味は報酬なしで活動するということではなく、収益を目標にしていない、利益を外部に配分しない、ということである。 活動で得た利益は、通信費、宣伝活動費やスタッフの給料などの必要経費となり、余った分は組織の使命・目的のために再投資される。
1998年、自民党から共産党まで全政党の議員が法案作りに協力して、議員立法として新しいNPO法が施行された。 日本のほとんどの法律は官僚が作っているので、国会議員が法案を作るのはきわめてめずらしい。 それだけNPOに国民的な関心があったということだ。 NPOとして認められるのは、保健・医療・福祉、社会教育、まちづくり、文化芸術、環境の保全、地域の安全、人権の擁護・平和の推進、国際協力、男女共同参画社会促進、子どもの教育、など17分野で、地域の場合は都道府県、広域団体は内閣府が認証にあたる。
あるNPOが特定非営利活動法人として認定されると、組織が法的に公のものとなり、法人名で銀行口座を開設したり、契約を交わしたり、土地の登記ができるようになる。 団体としての社会的な信用が得られるわけで、国や自治体からの補助金や民間からの寄付が得られやすくなる。 しかし、これからの新しい組織として期待されているいわゆる「草の根的」NPOだが、経営状態は非常に苦しい。 1980年代から、日本には多くのNPOが生まれたが、その多くは市民の自発的な参加による小さな団体である。 専従スタッフを除くと、参加スタッフはほとんどボランティアかアルバイトで、会員からの会費や有志からのカンパをおもな財源としていて、企業からの寄付はほとんどなく、専従スタッフはぎりぎりの生活をしている、というのが、今のほとんどの「草の根的・市民NPO」の現状である。

「グリーンピース」や「国境なき医師団」「アムネスティ」など、国際的に大きな力を持つNPOは、国や企業にとっては不利益になりがちな環境問題や、国境を超えた人命救助、人道支援、人権擁護などの活動で実績を積んできた。 今、日本で期待されているNPOのおもな仕事は、もともと政府や自治体などが行ってきた公共サービスの代行だ。 現在、政府・自治体の財政は最悪で、これまでのようなサービスを続けることがむずかしくなっている。 全国の自治体では、業務を民間やNPOに委託するところが増えつつある。 ゴミの収集、警備、スポーツ・文化施設の管理運営、学校給食、病院・診療所の運営、特別養護老人ホームの運営などが、民間へ委託されるようになった。 民間企業とNPOが委託業務の受注を巡って競争するわけだが、公共的なサービスの場合、利益を上げなければならない企業に対して、非営利のNPOは充分な競争力を持っている。
また、教育、医療、福祉・介護などで、求められるサービスが多様化するようになった。 国民が一丸となって近代化や高度成長を進めているときは、青少年の非行、家族機能の不全、老人の介護、失業などの問題は、ほとんどの場合「貧困」と結びついていた。 したがって行政の公共サービスの基本は、「貧困対策」として1つにまとめることができた。当然のことだが、社会が豊かになると、貧困以外の原因で問題が多発する。 そこで、実に多様な公共サービスが求められるようになる。 増える神経症患者へのケア、不登校児への教育サービス、ドメスティックバイオレンス(近親者による暴力)被害者のシェルター(避難所)設置やカウンセリングや社会復帰支援、リストラされた中高年やホームレスや低所得者への職業訓練・就職支援、高齢者への文化・娯楽・スポーツなどのサービスの提供、要介護認定者のためのいろいろな細かいケアなど、現代の社会では、必要とされる公共的なサービスは非常に多様化している。 行政が、そういったサービスすべてに対応するのは不可能で、民間への委託が進みつつある。 だが、今のところ教育や医療には株式会社の参入が認められていないので、ここでもNPOが仕事を得るチャンスがある。
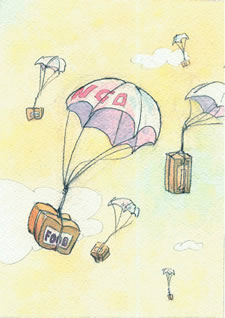
将来的に医療や教育の分野で株式会社の参入が認められるようになっても、同じコストがかかり、生産性や能力が同程度だったら、営利企業と非営利法人と、どちらに需要があるだろうか。 教育や医療、介護などのサービス機関への寄付や協力を考えている人は、営利企業と非営利団体とどちらを選ぶだろうか。 わたしは、NPOのほうに可能性があると思う。 出資に対する配当が不要な分、NPOのほうが有利で、しかもクリーンなイメージがあるからだ。 今後NPOが期待されているのは、教育や医療や介護の分野だけではない。 後継者不足に悩む農業、漁業、林業などの1次産業にもNPOは進出するかも知れない。
NPOの強みは、インターネットなどを駆使した情報収集・分析能力と、他のNPOとの国際的な連携だ。 農業・漁業・林業技術者のネットワークを作って、各地に派遣したり、環境NPOや国際交流NPOと連携して、地域の1次産業の再生と活性化を請け負うNPOが誕生するかも知れない。 伝統工芸や伝統芸能や文化事業・イベントなどでもNPOの力が必要になるかも知れない。 たとえばある自治体が地域を活性化しようとするとき、現状では、経営コンサルタントやシンクタンクなどに高い報酬を払ってアイデアを出してもらったりする。 だが、いろいろなネットワークを持つ複数のNPOが協力すると、どういうことができるだろうか。 まずその地域の地場産業を調査し、有力なものを選んでIT化を進め、仕入れ先を海外に求めたり、投資ファンドを探したり、新しいビジネスモデルを示したり、大学と協力して必要な特許などを紹介したり、さまざまなことが可能になるかも知れない。 そしてたとえば手造りの家具だったら、内外のデザイナーを紹介したり、販売経路を変えたり、環境への配慮についてアドバイスしたり、異なる分野の情報とネットワークを活かした対応が可能だ。
くり返すが、NPOはボランティア団体ではない。 収益を上げるために努力し、スタッフには報酬がある。 将来的に、NPOの成功例が多くなると、逆にNPOに参入してくる営利企業が現れる可能性がある。 投資家への配当が最優先され、利益が上がらなければ、現場の責任者はもちろん、最高経営者もクビになるのが、現代のグローバルな企業競争だ。 もともと日本では、地域や従業員のためにという基本姿勢で事業を行ってきた企業が多かった。 グローバリズムに従い合理化をくり返して株主のために利益を上げるより、地域の再生や従業員の健康や幸福を優先させ、利益よりも社会的な価値を上げ、人びとから感謝されることを選んで、NPO化を検討する企業が増えるかも知れない。 すでにアメリカや欧州の多国籍企業の中には、おもに環境保全の分野だが、NPOのスタッフをスカウトしたり、実際にNPOと業務提携する企業が増えている。
これまで示してきたようにNPOには多くの期待が集まっている。 だが、日本のNPOの現状は決して楽観できるものではない。 昔から存在する「公益法人」と呼ばれるNPOは、その許認可権を官庁が握っていて、これから期待されるNPO活動とはほとんど無縁の存在と化しているところが多い。 新しいNPOの進化には、そういった旧態依然の公益法人の改革が必要だし、またNPOへの課税のあり方も再検討される必要がある。 さらにNPOへの寄付金への税控除の問題も早急に検討されなければならない。 それは政治的な重要課題だが、もっと本質的な問題がある。 まず、財政的に自立できている「草の根NPO」「市民NPO」が非常に少ないということだ。 また、どのようなことができるかという広報・宣伝能力を持たないNPOが多いということ、そして、これが決定的なのだが、NPOに人材が集まらず、人材を育てるノウハウも組織もほとんどないということだ。 もちろんそういったNPOが抱える課題はそれぞれに関連し合っている。
日本のNPOは、まだまだ発展途上にあり、場合によってはこのまま役割を果たすことなく、消滅してしまう恐れもある。 もちろん一部には国際的に活躍し、メディアに取り上げられるようなNPOもあるが、そういった特別なNPOにしても、常に人材は不足している。 ただ、くり返しになるが、政府や自治体、それに町内会や地域社会などの、従来の公共団体では対応できない問題が増えているときに、相互扶助・セイフティネットとして、今のところNPO以外に機能できる組織はない。 つまり、現実が悲観的で、今後人材が育つ保証がないにしても、このままNPOを消滅させるわけにはいかないということだ。 結局NPOは日本では役割を果たせずに消滅した、という事態は、結局日本が内外の変化に対応できずに、危険で不安定な状態に陥ることを意味する。
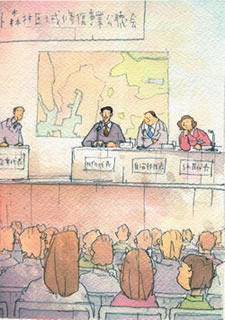
NPOを巡る状況を考えると、奇妙な思いにとらわれる。 政府や自治体よりも、あるいは営利企業よりも、NPOのほうがはるかに効果的に対応できるだろうという問題は、社会全体にあふれているし、これからも確実に増える。 たとえば自分の子どもが引きこもりになったとき、親はどこに相談すればいいのだろう。 現状では、地域の保健所か民間の精神科医、そして暴力がひどい場合には警察、あるいは全国に点在する数少ないボランティアグループに相談するしかない。 だが、カウンセラーを常駐させ、他の引きこもりの親たちや精神科医やフリースクールなどのネットワークを持ち、職業訓練や職業紹介の機能も合わせ持ったNPOがあればどうだろう。 出会い系サイトで出会った人から脅迫を受けているが親には言えないとか、援助交際で妊娠してしまったとか、地方から都市の盛り場に遊びに来て風俗店で働かされるようになったとか、そういう未成年はいったい誰に相談すればいいのだろうか。 行政では、たとえば教育と医療と警察とカウンセリングと職業訓練などがそれぞれ別系統の組織としてあって、ほとんど横の連絡がないし、全国的なネットワークもない。
ありとあらゆる分野で、行政と営利企業だけでは対応できない事態が生まれているのに、それに代わるべきNPOにはお金も人材も集まらない。 大学を出てもなかなか働き口が見つからず、不本意ながらフリーターになりアルバイトを続ける若者が200万人とも300万人とも言われているのに、NPOを作ったり、NPOに参加してみようという人材は非常に少ない。 将来的に日本の経済状態が多少良くなっても、雇用が一気に増えるわけではないし、新卒者の採用を減らし正社員を減らす傾向は変わらないのに、いまだに多くの若者が「就職」といえば「会社に入ること」だと思っている。 たとえ社員として会社に入ることができても競争が待っていて、能力がないと判断されれば、クビになるか、給料が優秀な同僚の半分とか3分の1になる、そんな状況が続くのはわかりきっているのに、ほとんどの若者は、いまだに「会社員」以外の働き方をイメージできない。
しかし、いずれ状況は変わるだろう。 重要なのは多くの人がNPOを作って成功させることだ。 成功して、収益を上げ、尊敬されるNPOが無数に誕生することが何よりも必要だと思う。 そうなれば、「成功」というイメージそのものがしだいに変わっていくだろう。 成功というのは、大きな会社に入って出世し、金持ちになって大きな家に住むことではない。 そのことに多くの人が気づくようになるだろう。 仕事に充実感を持つことができて、社会的に価値を認められ、豊かな人的ネットワークを持つこと、それがこれからの成功の基準だ。 日本のNPOは、人間で言えばまだ赤ん坊のような、未熟な状態にある。 だから、チャンスなのだ。 NPOで必要とされる知識や技術はほとんど無限で、金融から宣伝、医療や環境から芸術まで、どんな分野であれ、専門家は常に求めらている。 会社の知名度や実績にこだわって就職活動を続けるのか、知識と技術を磨いて起業を考えるのか、または信頼し合える対等な関係の仲間たちとNPOを立ち上げるのか、働き方の選択肢は1つだけではない。
村上龍
参考 『NPO入門』 山内直人 日経文庫
P.S.明日のための学習
13歳が20歳になるころには
-
いろいろな働き方の選択
-
IT[INformation Technology]
-
環境-21世紀のビッグビジネス
-
バイオは夢のビジネスか(commiong soon...)
