HOME > 特集記事 > P.S.明日のための予習 13歳が20歳になるころには? > 環境―21世紀のビッグビジネス
[INDEX]
- 1. 環境を守ることは合理的なこと
- 2. ビジネス化の背景と仕組み
- 3. 結論
-
4. 環境ビジネスの概観
- 4-1 太陽・風力・水素エネルギー
- 4-2 バイオマスエネルギー
- 4-3 リサイクル
- 4-4 エコマテリアル
- 4-5 ビオトープ
- 4-6 環境コンサルティング
- 4-7 グリーンツーリズム
- 4-8 調査・計画エンジニア
4. 環境ビジネスの概観
以下、具体的に環境ビジネスの概観を紹介するが、興味のある13歳は、今後環境や環境ビジネスだけを考えるのではなく、広い視野と興味を持ち続けて欲しい。環境は、わたしたちの生活のすべてに関わるもので、環境問題だけを勉強していればいいというものではない。環境を守る活動においては、たとえば法律家も、金融マンも医師も教師も科学者もアーティストも、ほとんどあらゆる職業の人材が必要となるからだ。
石油・石炭など化石燃料に代わる新しいエネルギーを開発し、それを管理したり、売ったりするビジネス。新しいエネルギーの代表として、太陽エネルギー、風力エネルギー、波力エネルギーなどがある。太陽エネルギーは、すでにソーラーシステムとして実用化されている。風力発電は、山の稜線などに立つ風車・ウインドファームが、クリーンなエネルギーの象徴になっている。また、21世紀は「水素文明の時代」といわれていて、水素と酸素を連続的に化学反応させながら電気エネルギーを取り出す燃料電池も注目されている。燃料電池の用途は多いが、無公害車としての自動車への応用はすでに実用段階に入っている。これらの新エネルギーは、基本的に大企業によって開発されていて、仕事として関わるためには、化学、工学、地質学、農学、生態学などの専門知識を身につけた上で、関連企業へ入社することが一般的だが、環境NPOに参加して知識と経験を積むというアプローチもある。
バイオマスエネルギーとは、廃材や食品廃棄物などの微生物が出す発酵熱をエネルギー源として利用すること。その中で木質バイオマスは、日本で大量に余り捨てられている廃材や、建築解体現場から出る建設廃材、それに間伐されて森林に放っておかれている廃木などを利用する。なかでも、木質ペレットと呼ばれる粒状の燃料は、おがくずや木の皮など、これまで捨てられていたものを利用するもので、家庭用の暖房エネルギーとして注目されている。木質ペレットは、林業や木工業と結びついていて、林業関連の、いくつかの企業が製造している。バイオマスには、木を原料とするもの以外に、下水の汚泥や食品廃棄物などをメタンと発酵させてエネルギーとする有機物バイオマスエネルギーなどがある。太陽光や風力に比べると、新しく参入する余地がある分野なので、意欲のあるベンチャー企業や自治体が開発に乗り出すと見られている。バイオマスの仕事に関わるには、化学や工学、それに農学などを学んで、そういった会社や自治体に就職するか、または環境NPOの一員となって事業に参加するか、あるいは思い切って起業するか、いくつかの選択がある。いずれにしろ、専門の知識と、人的なネットワークが重要なのはいうまでもない。
リサイクルというのは、「これまでは捨てていたもの」を再び利用したり、再び資源として使うということで、再利用・再資源化の総称だ。使い捨てを止めて、資源のムダ使いをなくすという意味の、「循環型社会」という考え方がその基本にある。廃棄物の、再利用・再資源化には、以下のように、いくつかの種類の、RE(再という意味)があり、それぞれにビジネスが生まれている。
| REFINE | 使用済み製品の分別・分解 |
| REDUCE | ゴミを減らすこと |
| REUSE | 再使用 |
| RECYCLE | (狭い意味で)廃棄物の再資源化 |
| RECONVERT TO ENERGY | 廃棄物を燃焼させてエネルギー回収 |
| REPAIR・REFORM | 修理・修繕(建築物の補修・改修も含む) |
上記の“RE”ビジネスには、大手から中小まで多くの企業がすでに参入しているが、「これまでは捨てていたもの」というのは要するにゴミのことなので、ゴミの種類だけREビジネスの種類もある、ということになる。医療系ゴミ、プラスチック、家具、家電、パソコン、パチンコ台、建設廃棄物、食品廃棄物(生ゴミ)、衣料品、靴、文房具、新聞や雑誌などの紙、電池、ガラス、そして家畜のウンコまで、とにかく古くなると、ありとあらゆるものがゴミになるわけで、その種類は、ほとんど無限だ。そういったゴミを、分別したり、分解したり、焼却したりする技術を開発したり、装置や機械を発明しただけで、それはビジネスとなる。たとえばプラスチックの廃材から何か抽出したり、廃棄されたパチンコ台のある部品を利用して再利用するというようなアイデアがあるだけで、それはビジネスになる。これからリサイクルは、「ビジネス」ではなく「産業」になっていくと予想される。リサイクルに関わる仕事は、ゴミや製品の種類だけ存在し、まさに限りがない。知識と技術とアイデアを持った人は、まさにゴミの山を宝の山に変えることができるかもしれない。
エコマテリアルとは、ものを生産するとき、ものを使用するとき、ものを廃棄するときに、地球環境を汚さない素材のことである。さらにリサイクル可能である素材、省エネルギーに適している素材も含まれる。地球環境への関心が高まるにつれて、企業がある製品を開発・製造する場合、コストやニーズと合わせて、「環境設計(エコデザイン)」という新しい考え方が必要になった。つまり製造において、どうやって使用する材料を減らすか、どうやって地球環境を汚さず、長く使えるものをつくるか、といったようなことだ。さらに、地球環境を汚さない素材・材料を選ぶことも、エコデザインの重要な要素となっている。具体的には、自然界の微生物が分解できるプラスチック素材(生分解性プラスチック)などがその代表だが、ほかに、有害物質を出さない塗料、大豆などの植物性油を使った印刷用のインク、鉛を使わないハンダやメッキ、クロムを使わない亜鉛メッキ鋼板、ハロゲンを使わない接着剤などがある。
生分解性プラスチックは、実用化に向けてさまざまな技術や製品が開発されているが、どうしても普通のプラスチックより割高になるために、現在のところプラスチック市場全体の0.1%以下という低い需要しかない。しかし、大手から中小の多くのメーカーがエコマテリアルの開発競争に参加している。今後、地球環境を守るための、法律や条例が整備されていくのは間違いないことで、そのための準備を怠った企業はやがて衰退してしまうと予想されるからだ。エコマテリアルの仕事に関わるには、化学的な知識や技術を学ぶことが不可欠だが、創造性や独創性も求められるだろう。
ビオトープとは、ドイツ語で生物を意味する「ビオ」と、場所を表す「トープ」が組み合わされてできた言葉で、ある地域・場所を、本来の自然環境に戻すということだ。つまり、工業化や工場・宅地開発などによって壊されたり、汚されたりした自然を元に戻し、野鳥や動物や昆虫や魚などの生物を呼び戻すということになる。環境教育の1つとして、学校の校内や、学校の近くに自然環境を復元する「学校ビオトープ」なども注目されている。小川や森、湖岸や海岸など、自然環境を復元するわけだから、どうしても事業規模は大きくなり、おもにゼネコンなどがその基本的なノウハウを蓄積している。だが実際には、土木工事の技術だけではなく、動植物などの生態系に関する情報や知識、土壌や水質などに関する化学的・地質学的な知識、ビオトープという考え方を地域に理解してもらうための説明能力なども必要になる。つまり、ビオトープの仕事に関わるには、土木・建設技術を学ぶとか、化学・地質学を専攻するとか、生物学や生態学を学ぶとか、さまざまなアプローチがあるということになる。
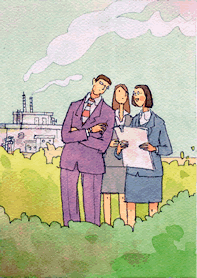
環境に関するコンサルティング・ビジネスで、グリーンコンサルティングと呼ばれることもある。企業が地球環境に配慮した経営や開発・製造を行うためのノウハウやマニュアルづくり、あるいは自治体や教育機関などの環境教育や研修などのコンサルティングも行う。ISO14001認証取得ブームが、専門的なノウハウやアドバイスを提供する環境コンサルタントの必要性をアピールすることになった。おもに、地球環境のことを考えた経営システムを考えたり、そのためのマニュアルをつくったり、従業員の意識や知識を高めるための研修などを行う。
これまでこの章で示してきたように、環境ビジネスは、本当に多くの、いろいろな分野に分かれていて、しかもいくつかの分野にまたがっているものもある。したがってコンサルティングも、ある企業が使用するエネルギーの効率を高め、省エネで経費を減らすというものや、そのために必要な設備を考えたり実際に作ったりするもの、産業廃棄物処理やリサイクルのためにアイデアを出すというものまで、実にいろいろな種類がある。さらには環境に配慮したエコホテル、エコツーリズムなどのコンサルティング会社も生まれようとしている。そういったコンサルタント業務で求められるのは、環境問題にくわしいだけという人ではなく、広い視野と知識、ビジネス感覚を身につけた人だと言われている。
環境を汚したり壊したりすることなく、自然について学ぶという要素を持つ旅行をエコツアーと呼び、都会の人が休みを利用して、農村で農作業などを体験したり、川などで生態系に触れたり、漁村で地曳き網などを体験することをグリーンツアーと呼ぶ。ヨーロッパで始まったこういった新しい「観光旅行」が日本にも広まってきて、グリーンツーリズムと呼ばれるようになった。旅行会社が企画するものから、自治体が主催するものまでさまざまだが、環境にくわしいコーディネーターやガイドが必要で、地元の住民やNPO・NGOが協力するケースも多い。環境に配慮した宿泊施設(エコホテル、エコリゾート)も増えている。地域や自治体によっては、過疎で廃校になった小学校の校舎を改造して旅行者が泊まれるようにしたり、田植えや山菜採り、炭焼き、わら草履づくり、そば打ち、陶芸・民芸品作りなど季節に合わせたイベントを催しているところもある。グリーンツーリズムの仕事に関わるには、いろいろなアプローチがあるが、基本的に地域に根ざしたビジネスなので、その土地・地方の自然に敬意を持ち、風習、生態系などにくわしいことが条件となる。
都市計画や建設計画が新しく立てられたときに、その地域・場所の生態系や環境について調査を行う。建設コンサルティングの会社で働くのが一般的で、水質調査、大気調査、騒音調査、生態系調査など、専門分野に分かれている。技術士や生物分類技能検定の2級以上を持っていると就職に有利である。
村上龍
参考 : 『新・地球環境ビジネス 2003-2004 自律的発展段階にある環境ビジネス』 エコビジネスネットワーク編 産学社
協力 : (株)伊藤忠商事地球環境室、(株)三菱製紙経営企画部・技術環境部
P.S.明日のための学習
13歳が20歳になるころには
-
いろいろな働き方の選択
-
IT[INformation Technology]
-
環境-21世紀のビッグビジネス
-
バイオは夢のビジネスか(commiong soon...)
