HOME > 特集記事 > P.S.明日のための予習 13歳が20歳になるころには? > 環境―21世紀のビッグビジネス
[INDEX]
- 1. 環境を守ることは合理的なこと
-
2. ビジネス化の背景と仕組み
- 2-1 国際環境条約
- 2-2 増税される政府予算と進む法整備
- 2-3 環境税の導入
- 2-4 国際規格ISO14001
- 2-5 森林認証制度FSC
- 2-6 環境NGOと企業の連携
- 3. 結論
- 4. 環境ビジネスの概観
2. ビジネス化の背景と仕組み
環境問題のビジネス化を促す仕組みとしては、まず国際環境条約があげられる。1972年にストックホルムで開かれた国連人間環境会議で、人間環境宣言が採択されたが、80年代に入って、地球規模で環境問題に取り組むという基本姿勢が明確になり、90年代には、リオ・デ・ジャネイロで地球サミットが開催され、「地球環境を積極的に守る」というグローバルなうねりが本格化した。国際的な法規制も強くなりつつある。また、地域的な2つの国や、複数の国の条約への取り組みも始まっている。たとえば急速に工業化が進む中国の酸性雨は、日本にも大きな影響を及ぼす。中国の環境問題は日本の環境問題でもあり、将来的に2国間で環境条約が結ばれ、共同で解決に当たるという事態も考えられる。そして、地球規模での環境問題への取り組みは、世界市場の基本的な約束事となりつつあって、今後貿易や取引において、環境への配慮が足りない企業はしだいに不利になることが予想される。
国内では、環境関連の政府予算が増え、法律も整備されつつある。環境省は「持続可能な社会」の実現を進め、環境ビジネスを支援するための予算を増やしている。持続可能な社会とは、温暖化で地球環境が破壊されたり、資源が枯渇することのない社会という意味で、環境を考えるときの1つのキーワードである。経済産業省は省エネルギーや新エネルギー行政を進めるための予算を増やしている。新エネルギーとは、太陽光発電や、風力発電、それに微生物の発酵を利用したバイオマスエネルギー、燃料電池、水素エネルギーなどだ。しかし今のところ、これまで通り原子力発電や石油・天然ガスへの予算も確保されているから、はっきりと新エネルギーへの転換を打ち出したとは言えないという指摘もある。
国土交通省は、これまで続けてきた自然を破壊する土木建設公共事業を止めて、自然再生型の事業を進めるとしている。その他にバイオマス事業を進めるとする農林水産省、それに環境教育を重視する文部科学省などが予算の配分を環境に移しつつある。それら省庁の予算配分については、欧米先進国の真似をしただけの中途半端なものという批判もある。しかし、国家予算がつくということは、現実的にお金が動くということで、とりあえず環境ビジネスのチャンスは増える。法律では、「循環型社会基本法」が施行され、さらに、容器包装リサイクル法、食品リサイクル法や自動車リサイクル法、建設リサイクル法などが全面施行された。企業や個人に対し、廃棄物のリサイクル・適正な処理を義務づけるものである。さまざまな生産物のリサイクルが義務づけられると、そこに新しいビジネスが生まれる。たとえば古くなって捨てられるパチンコ台などで再利用部分が増え、多くの企業が新しい再生技術に設備投資を始めることになる。
また、いろいろな形の環境税も考えられている。京都議定書で、温暖化ガス排出量を減らす目標が示されたが、その実現のための炭素税が日本でも検討されている。炭素税は、石油や石炭など、燃料のなかの炭素の含有量に応じて税を課すというものだが、フィンランド、スウェーデンなど欧州の一部ではすでに導入されている。日本で検討されているのは、たとえば燃費が悪い車の自動車取得・保有税などを高くする燃費比例型の炭素税などである。しかし炭素税が有効だとわかっていても、企業や個人にとっては高いコストになるわけで、当面の経済活動は圧迫されることになる。本格的な炭素税の導入はまだ先のことになるかもしれないが、国際的な大きな流れとして、今後環境税の導入は本格化していくだろう。そのための新しい開発戦略や資金を持たない企業は淘汰されることになり、またそこで新しいビジネスの可能性が生まれる。つまり炭素などの排出をできる限り押さえる技術を開発しないと国際競争に勝てない時代になるので、企業はそのための設備投資を行い、そこに新しいビジネスが生まれるということだ。
さらに、企業などが環境へ配慮する動機づけとして、ISO14001に代表される国際規格の取得がある。ISO14001は、ISO・国際標準規格が認証する環境マネージメントシステムの国際規格だが、品質保証規格のISO9600シリーズの取得で各国に後れを取り苦い思いをした日本企業は先を争ってISO14001認証取得を目指すことになった。03年6月現在ISO14001を取得している日本の企業・事業所は1万3000を超える。ISO14001は、たとえば工場廃棄物の数値を規制しているわけではなく、社員にどのような環境教育を行っているかとか、事業所の電力コスト削減にどう努力しているかとか、環境への取り組みを問うものだ。
日本では、製造メーカーだけではなく、自治体や大学、各地の商工会議所、ゴルフ場から地域のカントリークラブまで、ISO14001認証取得ブームが起こり、飲食店やスーパーや歯科医にまで「ISO14001を取得しませんか」という勧誘の電話がかかってくるようになった。コンサルティングビジネスが盛んになっただけだという批判もあるが、環境マネージメントシステムという国際規格によって、企業が環境に配慮するようになったのは事実である。だが、ある程度コストがかかるので、途上国の企業にとってISO14001認証取得は簡単ではない。だからISO14001による環境マネージメントシステムは、ISO14001を取得していない企業との取引を規制することで、途上国からの輸入増加を抑えようとする先進国に有利なシステムだという批判もある。
しかし、確かに環境マネージメントシステムは、これからの企業経営にとって不可欠になりつつある。環境への配慮がない経営姿勢は、国内でも、国際的にも忌み嫌われるようになった。公害を出したり、エネルギーを大量に消費したり、廃棄物や化学物質をまき散らしたり、自然環境を破壊したりする企業は、環境NGOから名指しで攻撃・批判を受けたり、住民から訴訟されたり、多大なコストを払わなければならない。さらに最近では、ISO14001の取得が、ビジネスのパートナーを選ぶときの条件になることもある。環境への配慮がない、あるいは配慮が足りないと見なされた企業は生き残れないような仕組みができつつある。
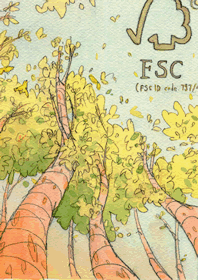
経済合理性を利用しながら環境を積極的に守る仕組みは、国際規格だけではない。たとえばFSC(Forest Stewardship Council A.C : 森林管理協議会)という国際NGOが運営する森林認証制度がある。国内の大手製紙業界でいち早くFSC認証に取り組んだ三菱製紙の場合、所有する南米チリの森林で、林道からの土砂の流出を押さえ、野生動物の生息地を保護し、水辺の保護林は一切伐採しないというような厳しいFSCの基準をクリアし、認証を得た。これまで環境に配慮した印刷紙といえば、再生紙だけだった。だが再生紙は、印刷でカラーグラビアなどの発色が悪いとか、古紙パルプからの生産時に大量の石油を使うなどの欠点があった。FSCの認証を得て、その証であるロゴマークをつけるためには、認証森林からの木材チップ使用というだけでは不十分である。その他の加工、流通、印刷部門すべての過程で、CoC(Chain of Custody)という認証を得る必要がある。
CoCには認証番号があり、その番号をたどることで、その紙の来歴を知ることができる。つまりどの森林で伐採され、どのルートで輸入され、どの工場で加工され、どこで印刷され、どのような流通経路をたどったかという、ほぼ完全なトレイサビリティ(traceability:起因・経路確定性)が確保されている。FSCの認証制度は、「再生紙」の考え方を超えている。つまり、資源のムダ使いを止めるという考え方から、原生林を守るという積極的な環境保全への転換を見ることができる。三菱製紙の場合、現段階でのFSCの認証紙は、紙パルプ年間総生産量の1%程度だそうだが、今後チリ以外のエクアドルやオーストラリアの所有林でのFSC認証を取得していくことがすでに決まっているらしい。
いうまでもなく、森林は、木材、紙パルプの原材料だけではなく、地下水や、豊かな微生物と土壌、薬となる植物や食材、そして何よりも「酸素」を提供する地球の貴重な資源だ。森林を積極的に保護する仕組みであるFSC認証を中心的に担っているのは、これまで企業側と対立しがちだった先鋭的な環境NGOである。企業の中には、環境NGOの人材を環境マネージメントの責任者として迎えるところも増えている。企業、自治体、それにNGOや市民グループなどが共同で環境保全活動に当たるという大きな流れが現実のものとなっている。今後、「環境に配慮した企業がより有利になる」という傾向が弱まることはない。
村上龍
P.S.明日のための学習
13歳が20歳になるころには
-
いろいろな働き方の選択
-
IT[INformation Technology]
-
環境-21世紀のビッグビジネス
-
バイオは夢のビジネスか(commiong soon...)
