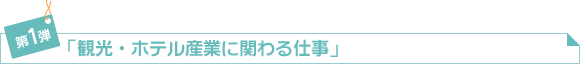HOME > 特集記事 > 中・高校生に送る 業界特集 > 「観光・ホテル産業に関わる仕事」
いま、観光・ホテル産業の周辺には、勢いよく追い風が吹いています。
国の支援、新たな都心ホテルの開業、これから見込めるたくさんの観光客…。
お客様の目に触れる場所でも、直接見えない裏方でも、たくさんのプロたちが、旅する人たちをここちよくもてなすために、日夜、技を磨いています。
「人が好き」「喜ばせるのが好き!」というサービス精神たっぷりあふれる人ならば、「好き」を仕事にできる格好の場所かもしれません。
観光・ホテル産業の「いま、これから、注目したいポイント!」を13hw編集部がご案内いたします!
「観光産業」から思い浮かぶ職業は何でしょう? さっそうとしたホテルマン、にこやかなバスガイドさん、頼れるツアーガイド…。ぱっと10種類以上思い浮かぶ人はすごい!そう、旅に関わる仕事には、たくさん種類があるのです。
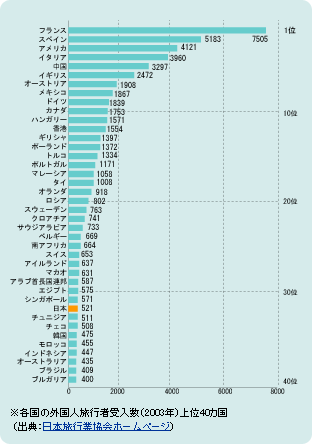
では、いったい日本や世界で、どれだけの人が「旅」をしているのかというと…。
昨年1年間に海外へ出かけた日本人は1,683万人。これは、だいたい大阪府と神奈川県の人口を足したぐらい。それに比べ、日本へ来た外国人は3分の1のわずか614万人。去年、海外旅行をした人は世界で7億人もいたので、そのうちのほんのわずかです。チュニジア、ハンガリー、クロアチア、マレーシア、南アフリカ…。意外ですが、日本はこれらの国々よりも外国からの旅行者が少ないのです。国別の外国からの旅行者受入数は世界第32位、アジアの国々でも5位以下です。ちょっと少ないですね。
国内を旅する日本人の数も10年以上横ばい状態で、1回の旅行にかける費用も低下傾向。国内の移動がどんどん便利で楽になっていくと、「日帰りで行けるね」「1泊で十分だ」と、かえってゆとりのない旅になる、ということもあるようです。
一方、働く場としての日本の観光産業も、海外のそれと比べるとまだまだ発展途上のため、
「観光産業の場合、日本では直接・間接を合わせて国民の5ないし6%の人が従事していると考えられています。しかし、アメリカではこの2倍の人が、ヨーロッパの主な国でも10%以上の人が観光産業に関連しているというところが少なくありません。」(『やさしい経済学』竹中平蔵)と指摘されています。
そんな状況下、日本政府は観光政策へ力を入れ始めました。平成15年度に開始した「ビジット・ジャパン・キャンペーン」。多くの外国人に日本を訪問してもらうため、国土交通省を中心に世界各地でさまざまなキャンペーンが実施されています。その一部を挙げてみましょう。
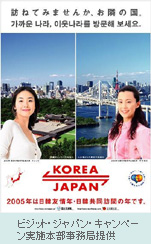
- 小泉総理が英語で、石原観光立国担当大臣(当時)が中国語で、それぞれ「YOKOSO!JAPAN」PRビデオに出演。
- 韓国では、観光広報大使の木村佳乃さんがチェ・ジウさんとPRポスターで共演。
- 米国で開催の「OTAKON2005」(オタクとコンベンションを組み合わせた造語)にブースを出店、アニメ文化を積極的にPR。

- 航空会社が「YOKOSO! JAPAN」デザインの飛行機を就航させ、空港会社もロゴ入り看板で外国人客を迎えるなど、政府と協調した動きを見せる。
などなど・・・
小泉総理大臣は、平成16年1月の第159国会で「2010年に日本を訪れる外国人旅行者を倍増し、「住んでよし、訪れてよしの国づくり」を実現するため、日本の魅力を海外に発信し、各地域が美しい自然や良好な景観を生かした観光を勧めるなど、「観光立国」を積極的に推進します」と宣言をしました。
今年からは日本経団連も積極的に動き出し、以下の3点に絞ったイメージ戦略が大事だと述べています。(「日本経団連タイムス」No.2773)
第1のイメージ戦略「伝統とハイテクの国」では、最先端技術と伝統文化、ポップカルチャー(アニメなど)といった観光資源を活用し、改めて「現代の文化国家日本」のイメージを発信・定着させる。
第2のイメージ戦略「四季と食文化の国」では、起伏に富んだ風土と気候、それらにはぐくまれた独自の食文化をアピールし「行ってみたいと思う国」にする。
第3のイメージ戦略「安全・安心ともてなしの国」では、我が国の安全性と真面目で親切な国民性をアピールし、同時に国民一人ひとりも、海外からの観光客をもてなす意識を高めてほしい。
このように政財界が力を合わせて取り組んでいる観光産業は、これから確実に成長が見込める分野なのです。
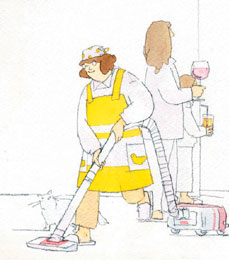
では、人々が「旅」に関わる場所で働くには、どういう準備が必要で、どこで学べるのでしょう。
世界のトップレベルと言われるのがアメリカにあるコーネル大学。アメリカ有数の難関大学ですが、看板学部の1つがホテル経営学部です。学生はイサカという小さな田舎町で、ホテル経営に必要なあらゆるノウハウを学びます。多くの卒業生が世界の有名なホテルやレストランを舞台に活躍しています。
海外では観光学部を持つ大学が多数存在しており、前掲『やさしい経済学』によれば、オーストラリアでは3分の2の大学にツーリズム&ホスピタリティ関連の学部があるそう。しかし日本では、観光についての学びの場はまだまだ…といったところです。
最近でのトピックスでは、今年の11月8日から13日まで、大分県別府市で「世界観光学生サミット」が開かれました。世界21の国と地域、78大学の290名(そのうち国内は32大学151名)の学生が「観光の発展と人材育成」について活発な議論を交わし、最終日には小泉総理も訪れ学生たちを激励しました。今後、地方の大学・短大、新設の教育機関では観光学部・学科を積極的に設置する動きがあります。また、独自の教育システムを持つ各ホテル専門学校でも、一流の人材を養成するための実践的カリキュラムの充実が図られています。
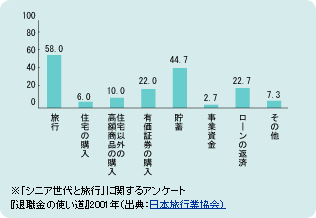
これまで、日本人の海外旅行に比較して、訪日する外国客はあまりに少ないものでした。が、今は政府が中心となって、積極的に国内外の観光業の環境を整え、経済界や教育機関が後押しをしている状況です。今後の旅行業界で働く人にとっては、それらが追い風になるでしょう。 また、2年後には「団塊の世代」(*2) が定年になり、多くの退職者が発生します。これは2007年問題と呼ばれていますが、統計によれば「退職金を得たら、まず最初にすること」の1位が「旅行」。2007年以降、リタイア世代による大規模な旅行ブームが来る可能性は十分あるのです。
また、ホテル業界では別の「2007年問題」がささやかれています。都心では「ザ・リッツ・カールトン東京」「ラッフルズホテル」「ザ・ペニンシュラ東京」など外資系ホテルを中心に、開業予定が7棟もあります。ホテルの生き残りをかけた「2007年問題」なのです。他の都内ホテルも改装・改修に力を入れており、この先、東京のホテルは競争がますます厳しくなるでしょう。これは、優雅な宿泊を望むリタイア世代にとっては、ある意味で「選ぶ楽しみ」が増えるということ。また、ホテルの数が増えると世界的なコンベンションなどにも対応可能となり、都市としての東京のステイタスが確実にランクアップします。そういう意味では、楽しみな「2007年問題」とも言えますね。
注目されるもう一つのポイントは、オリンピック誘致運動です。今年、東京と福岡が招致に名乗りを上げました。もし2016年の開催が実現すれば、長野オリンピック以上に多くの外国人が日本を訪れることになります。美しい都市景観のための設備投資が行われ、さらなる景気の改善も十分見込めます。 このような追い風の中でも、サービス産業の基本はやはり「人」です。それぞれの仕事場で、旅に関わるプロが「おもてなしの心」を発揮しているのです。
2016年、もしも日本でオリンピックが開催されるなら、観光産業で働く人々は多くの刺激を受けるでしょう。いま13歳の君たちならば24歳、社会の入り口に立つ時期です。観光に関わる仕事を通じて “人をもてなす技術”を得る。その技術が一生を支えるかもしれないなんて、ちょっと素敵かも!? 観光関係の職業は、裾野が広く展望も明るいし、まだまだ開拓の余地もあります。人と関わることが好きならば、君たちの目の前にはとても魅力的な仕事場が拡がっているのです。
≪用語解説≫
(*1) 「職業観」…働くことについての、その人なりの考え方。
(*2) 「団塊の世代」…第二次大戦直後、1947(昭和22)年からの第一次ベビーブームで生まれた世代。間もなく60歳というリタイアの時期を迎えようとしている。
(*3) 「ホスピタリティ」(hospitality)…気持ちよくもてなすこと。おもてなしの心。「手厚いもてなし」を意味するラテン語から生まれた語で、hotel(ホテル)、hospital(病院)も同じ語源。
≪参考文献≫
『やさしい経済学』(竹中平蔵・幻冬舎文庫)
「グローバル観光戦略」(国土交通省発行)
「ホテルの仕事がわかる本」「最新ホテル業界事情」(財団法人 日本ホテル教育センター発行)
中・高校生に送る「業界特集」
-
地域のくらしをバックアップする
司法書士の仕事 -
生活空間と街をつくる
総合建設業の仕事 -
巧みなストーリー展開で、視聴者のハートをつかむ
ドラマづくりの仕事 -
大海原が人生のステージ
海運の仕事 -
“キレイ”をつくるプロフェッショナル
美容業界での働き方 -
おいしい仕事、教えます
料理業界での働き方 -
“音楽”を仕事にしたい人に
音楽業界での働き方 -
観光・ホテル産業に関わる仕事