HOME > 特集記事 > 13編集部 シリーズ特集 > 生きる力を身につけさせるマネー教育
「小学生が株取引」「子ども向け金融セミナー大盛況」
最近、金融や経済に関心を寄せる子どもたちの話題をよく耳にします。
「子どもがお金についてあれこれ口を出すなんて―」と大人が眉をしかめたのは過去の話。早いうちから金銭管理能力を磨かせたい親御さんや、経済のしくみを理解する機会を与えたいと考える教育関係者の方々も増え、政府でも若年層向けのマネー教育に焦点をあてた方針を打ち出しています。
お金について知りたいという子どもたちの好奇心に的確に応え、彼らに生きる知恵を体得してもらうため、企業、学校、そして家庭では、どんな取り組みが行われているのか。現代マネー教育事情を紹介します。(13hw編集部)
[INDEX]
マネー教育先進国アメリカでは
日本では敬遠されがちだったマネー教育ですが、海外では、かなり以前からその必要性が重視され、積極的に取り組む国も少なくありません。
中でもマネー教育先進国といわれるアメリカでは、子どもがお金について学ぶのは当たり前。幼稚園からハイスクールまで、発育段階に合わせたマネー教育の環境が整備されています。各幼稚園や学校では、経済教育NPO(非営利団体)などの協力を得たマネー教育プログラムを導入。生徒が実際に株取引を行ったり、企業家や経済人が講師となってビジネスシーンでの旬な話題やこぼれ話を披露するなど、大人も参加したくなる興味深い授業が展開されています。
こうした背景には、多民族が暮らす土地ゆえさまざまな通貨が流通している、クレジットカード社会である、日本に比べ医療費がかなり高額……などなど、個人個人がしっかりとした金銭管理能力を身につけなければ生き抜いていけないというシビアなお国事情もあるのでしょう。しかし、幼少期から経済・金融の世界と接点を持つことで、お金の大切さ、お金を得ることの大変さを知り、社会生活の基礎知識や働くことへの意欲を養えるなど、子どもたちが得るものは大きいようです。
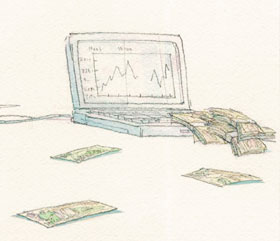
平成17年は日本のマネー教育元年
マネー教育先進国に遅れをとりつつも、ようやく日本でもマネー教育の必要性が注目され始めています。とくに昨年は一連の企業買収騒動などの影響で“M&A”、“企業価値”といった言葉が身近なものとなり、メディアで注目される若手経営者に憧れて起業家を目指したり、株式投資に乗り出す若者も増えています。
さらに、金融商品・サービスの多様化が進み、消費者の選択肢は拡大。ペイオフ(※注)解禁拡大や社会保障制度改革など、社会のしくみにも変化が生まれました。一方でヤミ金融被害やネット詐欺といった、若年層をも巻き込んだ金融トラブルが相次ぎ、経済・金融に対する世間の関心が集まりました。
“今”を生きるためには、早い段階から的確な金融知識を身につけることが必要。そうした社会的ニーズが高まる中、金融広報中央委員会は「平成17年は金融教育元年である」と位置付け、全国の幼稚園、小・中・高等学校での金融教育を推進。金銭・金融教育研究校(121校)へのマネー教育サポートをはじめ、公開授業や教員向けセミナー、金融教育フェスティバルの開催など、積極的な広報活動を展開しました。また、同会主催サイト「知るぽると」でのマネー情報提供も行っています。
※注)ペイオフ…金融機関が破綻した際、金融機関が加入している預金保険機構が預金者に一定額の保険金を支払うという預金者保護のしくみ。以前は預金額が全額保護されたが、平成17年4月のペイオフ凍結解除以降は一金融機関につき一預金者1,000万円までの預金と利息が保護されることになった。
お金を理解することは生きる知恵を体得すること
政府や各機関も本腰を入れ始めたマネー教育。ここで、その目的について整理しておきましょう。前出の金融広報中央委員会事務局長の湯本崇雄氏は「金融教育とは社会を生き抜いていく力を養うものであり、具体的に以下の4つの目的がある」と語っています。
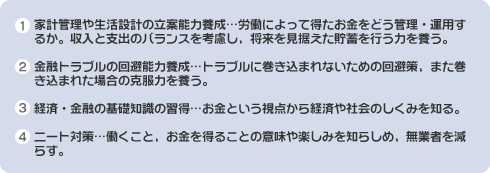 「教育マルチメディア新聞」05年05月07日号より/教育家庭新聞社
「教育マルチメディア新聞」05年05月07日号より/教育家庭新聞社
“マネー教育=お金もうけや貯蓄のノウハウを伝授”といった印象を抱かれる方もいらっしゃるでしょう。しかし、単に金銭管理のテクニックを指導するのが目的ではなく、その根本には「現代社会を生き抜き、将来の日本を支える若者を育てたい」との思いが込められています。
全国各地でマネー教育に関するさまざまな取り組みが行われています。その中でも大好評を博している企画や催しを紹介します。現在参加者募集中のイベントもあるので、興味のある人はぜひアクセスを。
「金融とか経済って複雑で難しそう…」そんなイメージを払拭し、子どもたちが金融・経済の世界と楽しくふれあいながら知識を習得できるサイトを集めました。
社会生活に不可欠な “お金”。そのしくみを学び、知識を蓄えることは、社会を知り世間を渡っていく力を身につけることにもつながるんですね。マネー教育の参考になる7冊を紹介します。

「中学生・高校生のための金銭感覚講座」
武永脩行・著、こどもくらぶ・編集(同友館)
子どもの目線で経済感覚をとらえ、通販・ネットショップ・カード払いなど目に見えないお金の流れについても、わかりやすく解説。お金の魔力をコントロールできる知恵と知力を身につけられる一冊。
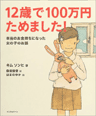
「12歳で100万円ためました!
―本当のお金持ちになった女の子のお話」
キム ソンヒ・著、桑畑優香・訳、はまの ゆか・絵(インフォバーン)
日々の暮らしの中で節約を重ね、工夫しながら100万円をためた韓国の小学生の実話。主人公の少女に感情移入して読み進めるうちに、“お金を得る”ことの意味や大切さ、充足感、難しさを体感できる。
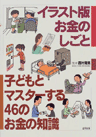
「イラスト版お金のしごと 子どもとマスターする46のお金の知識」西村隆男・監修(合同出版)
生活、借金・投資、金融、消費者の4つのカテゴリーに分類された、お金にまつわる基礎知識をイラスト入りで解説。通帳のつくり方やATMの引き出し方、悪徳業者の対処法なども実践的に紹介しており、生活ガイド本としても役立つ。

「お金のしつけと子どもの自立
金銭感覚を身につけさせる50のポイント」
子育てグッズ&ライフ研究会・編集、寺田令子・マンガ(合同出版)
編者は消費生活アドバイザー等の資格を持つ、子育て中の母親グループ。お小遣いの与え方や、子どもと一緒に買い物に出かけた際のコツなど、実践的なしつけのポイントを事例で楽しく説いている。
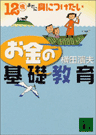
「12歳までに身につけたいお金の基礎教育」
横田濱夫・著(講談社文庫)
ファミレスや回転寿司、スーパーマーケットなど、さまざまな場面において健全な金銭感覚を身につけるコツを伝授。悪徳商法から身を守る方法や子どもが恐喝された際の対処法など、お金トラブルから身を守る具体策も満載。親と子で学ぶ超経済入門。
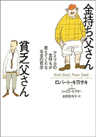
「金持ち父さん貧乏父さん」
ロバート キヨサキ&シャロン L.レクター・共著、白根美保子・訳(筑摩書房)
高学歴なのに収入が不安定な“貧乏父さん”と、13歳で学校を中退したものの今は億万長者という“金持ち父さん”。二人の父親の人生を追いながら、お金に関する著者の哲学や「経済面でのリテラシー」が語られている。
お金を知ることは社会を知ること。マネー教育の現状についてご紹介してきましたが、子どもたちに金融について正しく理解してもらうことの大切さを、編集部でもあらためて実感しました。昨年の金融教育元年を経て、全国での取り組みがますます盛んとなる中、この特集を学校や家庭でのマネー教育にお役立ていただければ幸いです。
13hw編集部特集
この国の”仕事選びが変わりはじめている
-
賃金構造基本統計調査にみる年収
-
ズバリ!留学って仕事に役立つの?
-
社会人から中高生に贈る231のメッセージ
-
「持続可能な社会を目指そう!」仕事選びでも注目される“環境”というキーワード
-
「若者の自立と挑戦を応援したい!」地域密着型の就労支援
-
「お金についてきちんと理解したい」子どもたちに生きる力を身につけさせるマネー教育
-
「進路指導」から「キャリア教育」へ~学校の新しい取り組み~
-
113万部のベストセラー「13歳のハローワーク」を考える







